 トップヘ
トップヘ  現状へ
現状へ
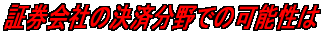 (2000.4.12新規作成)(2001.3.1ほんの一部追加)
(2000.4.12新規作成)(2001.3.1ほんの一部追加)
1.証券会社が決済を行なう背景
(1)決済面の充実メリット
- 銀行業務は大きく分けて、資産運用、決済機能があり、資産運用を含めた家計の総合サービス(資産負債管理)によって銀行顧客の固定化、リテール対応をすすめようとしている。
- 証券会社の口座をつくる場合、自宅住所の分かる本人証明書類、勤務先、年収、自宅の種別など、殆どクレジットカード与信にそのまま使える情報+具体的な資産の把握ができている面では、証券会社の有利性がある。
- 証券会社は、自社内での総合化(資産内の移動:例えば株式購入代金を中期国債ファンドから等)はできあがってきているが、銀行との間での決済は振込み先としての関係に留まっている。
- この点では、例えば証券購入代金をデビット決済できれば、銀行の預金から、証券会社に資産が移ることになる。
- 資産運用ノウハウのある証券会社なので、移った資産は証券会社内に留まる確率は高い。
- たとえば、証券を売った代金は証券会社内で中国ファンドやMMFといった資産にして運用する、または債権購入に充てることは容易であり、インターネットのホームトレードでも、指示できる。
- 逆に銀行側からみれば、銀行預金が固定化できずに、証券会社に流出して戻って来ないという可能性が考えられる。
- それが、デビットカードで金融商品の決済は現在?となっている理由の1つではないだろうか。
- 銀行としては、金融商品販売の窓口となって、家計管理によるリテール化という面では、証券会社と競合することになる可能性がある。
- もっとも直接的には振込み手数料よりデビットの手数料収入の方が低いといった単なる比較論もありうるが。
(2)証券会社の決済面での課題
- 銀行のつくりあげてきた全銀手順による、他行からの預金引出しといったネットワークが、一部証券会社間であるだけで、銀行、郵貯(郵貯もないので相互接続に積極的)のネットワークとは切り離されている。
- 利用者からみれば、郵貯の場合のように、郵便局で現金引出して銀行に入金といった不便さを解消して、その場で送金したい。
- 銀行と証券会社との相互接続がされれば、利用者にとっては便利であるが、資金がどちらに流れるかがポイントとなろう。
(3)トヨタはなぜ証券会社形態で決済をしようとしているのか。(個人的考察)
- 車を購入する人を囲いこむには、資産を車に置きかえるという資産の移動という観点では証券会社で決済ができれば良いのでは。
- 分割払いも証券総合口座から毎月引き落とせば良いし。
- 更に証券会社本体で可能かどうかは別として、個人へのローンやリースと組み合わせることも考えられます。
- 証券会社の総合口座で決済ができれば、資産を持った人の囲いこみは可能となります。
(4)松井証券が実質デビット決済を開始する(2000.5.21追加)
- 住友海上、三井海上の保険販売を、代理店として松井証券がインターネットで実施を発表しました。
- 保険料は松井証券のインターネット口座から決済。残高不足の場合は、保険契約不成立となります。
- インターネット上のデビット決済で銀行間の足並みが揃わない中で、証券会社による実質的なインターネットデビット決済がはじまることになります。
- 銀行によるインターネットデビットが始まった時点で、松井証券は、金融商品販売の加盟店として、松井MMF商品などの販売につなげれば、保険等の販売時点の残高不足も、即時解消できるようになるかもしれません。
- 松井証券、ネット外為取引参入:豪投資銀行(マッコーリー)と組む(2001.3.1)
交換レート設定などは、マッコーリーが行ない、24時間売買注文が出せ、自動的に外貨建て資産へ投資できる。
当初は最低単位100万ドルと、企業向けだが、松井の顧客基盤を利用して、個人の小口取引へ広げるとのこと、為替取引きは銀行といった垣根がなくなる。
2.導入する仕組みは(2000.5.21追加あり)
- 今回の私案方式で会員管理会社として証券会社が位置付けられ、インターネット専用にしておけば、ホームトレードの一環としてデビット決済が構築できることになります。何より運用が容易でマーケティングはe-mail等で安くあがる方式ができます。
- MMF等は、実質的に普通預金と同等の流動性をもっているので、MMF等でのデビット決済が現状の銀行預金のデビット決済と同様にできることになります。
- 一方、証券会社はインターネットデビット決済では、加盟店として、MMF等の金融商品販売が可能となります。
- したがって、デビット決済で購入したMMF等の残高で株式購入の決済もできるし、他のショップのデビット決済にも使える可能性があります。
 トップヘ
トップヘ  現状へ
現状へ
![]() (2000.4.12新規作成)(2001.3.1ほんの一部追加)
(2000.4.12新規作成)(2001.3.1ほんの一部追加)